アドラー心理学において、劣等感とは一般的な他人との比較における劣っているという感情とは違い、劣等感とは自分の理想とする姿と現在の姿のギャップを指していることは、別の記事でご紹介しました。

このアドラー心理学における劣等感は、人生をより良くするための起爆剤となることから、私は健全な劣等感と表記しました。
このように現状をさらに良くしようとするための力になる劣等感ではなく、一般的な意味での
- どうせできるはずながい
- どうせ私なんて
といったマイナス方向への姿勢のことを、アドラーは次のように名付けています。
それは、「劣等コンプレックス」です。
では劣等コンプレックスとは、どういう状態なのでしょう。
劣等コンプレックスとは
アドラー心理学では、劣等感を言い訳に使って、目の前の課題から逃げることを「劣等コンプレックス」と呼んでいます。
劣等コンプレックスの特徴は、
- 私には経験がないから、期待に応えられない
- 学歴がないから、稼げない
など、
「Aではないから、Bできない」もしくは「Aだから、Bできない」
という論理を多用することです。
ここで注目すべきことは、実際にAとBには因果関係がないことです。
- 経験がないことと、期待に応えられるかどうかは別問題です。
- 学歴がないことと、稼げるか稼げないかは別問題です。
しかし、劣等コンプレックスの人はAとBとの間に、因果関係があると思いたがる傾向があります。
アドラーは、この一見因果関係があるように思える事態を
「見かけの因果律」
と呼び、この見かけの因果律を理由に人生の課題に向き合わないことを
「人生の嘘」
と言いました。
劣等コンプレックスのある人は、しない理由やできない言い訳ばかりを探して、実際の課題から目を背けてしまっています。
そして、もしも経験があれば、もしも学歴があれば、私だって・・・、と可能性の中に我が身を置くことで、その問題を解決せずに済まそうと思ってしまうのです。
劣等コンプレックスにならないためには
アドラー心理学での健全な劣等感は、理想の自分との比較から生まれ、そのギャップを埋めようとプラスに働かせます。
一方で不健全な劣等感は、他者との比較から生まれ、見かけの因果律を多用することで劣等コンプレックスの状況を引き起こします。
そうならないためには、他者に勝った、負けたといった勝ち負けだけで判断することをやめることが大切です。
劣等コンプレックスとは、どんな状況なのかお分かりいただけましたでしょうか?
実は、劣等コンプレックスと真逆の状態もあります。
それは、優越コンプレックスと呼ばれるものです。
今度は別の記事で優越コンプレックスについてご案内します。

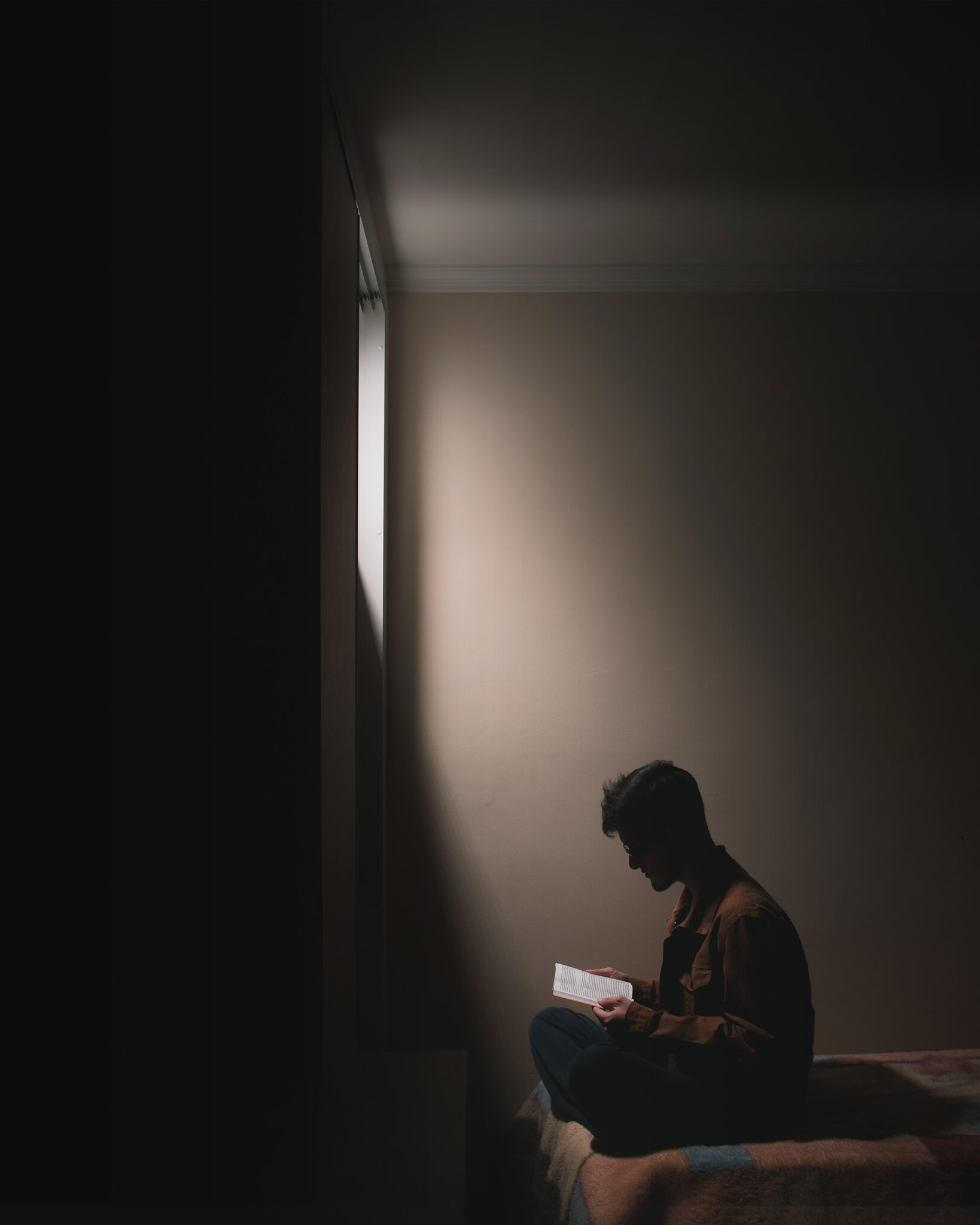


コメント